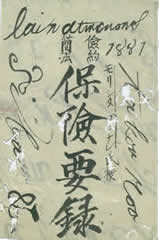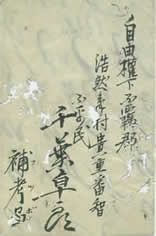千葉卓三郎の学習遍歴と深澤父子
五日市憲法草案を起草した千葉卓三郎は、嘉永5(1852)年6月17日に宮城県栗原郡白幡村(現:栗原市)に、仙台藩下級藩士の父千葉宅之丞のもとに生まれました。文久3(1863)年、11歳から仙台で大槻磐渓(仙台藩校養賢堂の学頭)のもとで学び、明治元(1868)年には師のもとを離れて戊辰戦争白河口の戦いに参戦しています。
この戦いで敗戦を味わった卓三郎は、様々な学問や宗教に真理探究の矛先を向け、皇学・浄土真宗・ギリシャ正教を学んでいます。特にギリシャ正教には傾倒し、上京して洗礼を受け、布教活動にも携わっていました。しかしその後も卓三郎の学習遍歴は治まらず、儒学・カトリック・洋算、さらにプロテスタントへと遷り変わっています。
その後、どのような経緯かはわかりませんが、明治12(1879)年頃から大久野、草花など秋川谷の各地で教職に従事し、明治13(1880)年4月下旬には五日市に下宿して勧能学校に勤めはじめています。おそらくは卓三郎と同郷の勧能学校初代校長永沼織之丞の導きがあったのでしょう。
五日市にたどり着いた卓三郎は、新しい知識を求めていた五日市の民衆に受入れられました。特に深澤名生・権八父子との信頼関係は厚かったようです。また、かつて五日市に住んでいた小田急電鉄創始者の利光鶴松は自伝の『利光鶴松翁手記』に「当時の出版されていた翻訳書の7~8割の本があり、誰にでも自由に閲覧させていた」と語っていますが、深澤家には豊富な蔵書があり、これらの図書を使って学習に励み、学芸講談会の活動を通じて地域の自由民権運動の質を高めるとともに、漢詩のサークルなどを通じて地域の文化にも貢献しました。
五日市憲法草案起草後の明治15(1882)年には結核が進行し、五日市の仲間からの援助を受けて療養をしていましたが、明治16(1883)年11月12日、31歳の若さで死去しました。
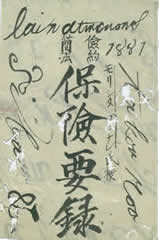
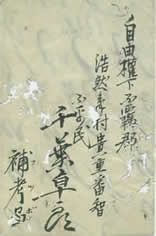
千葉卓三年譜
嘉永5(1852)年
6月17日 宮城県栗原郡白幡村(現:宮城県栗原市)にて出生 本名:宅三郎
父、仙台藩下級藩士、千葉宅之丞
8月 父宅之丞死去
文久3(1863)年1月~慶応4(1868)年2月
仙台にて大槻磐渓(仙台藩校養賢堂学頭)に師事(漢学)
慶応4(1868)年3月~明治元(1868)年9月
戊辰戦争白河口の戦い(白河城攻防戦・相馬駒ヶ峯の戦い)に参戦するも敗戦を経験
敗戦後、郷里に帰る 仙台藩の帰農令によって士族身分を喪失
明治元(1868)年11月~明治2(1869)年8月
松島にて石川桜所に医学を学ぶ
明治2(1869)年10月~明治3(1870)年11月
気仙沼にて鍋島一郎に皇学を学ぶ
明治3(1870)年12月~明治4(1871)年4月
桜井恭伯に浄土真宗を学ぶ
再び郷里に帰る
明治5(1872)年10月
義母さだ死去
この頃、金成で布教活動していた酒井篤礼のギリシャ正教集会に参加したと考えられる
明治6(1873)年4月
東京でニコライから洗礼を受ける クリスチャンネーム ペイトル千葉
帰郷後、郷里でギリシャ正教の布教活動を行う
明治7(1874)年3月~6月
神仏への不敬(伊勢神宮玉串や先祖の位牌を投棄)を理由に100日間投獄
明治8(1875)年4月ごろ
郷里を離れ上京 駿河台でニコライにギリシャ正教を学ぶ
明治8(1875)年5月~明治9(1876)年2月
市ヶ谷で安井息軒の門に入る(儒学)
明治9(1876)年4月~明治10(1877)年1月
神田猿楽町で仏人ウィグロー(ウィグルー)にカトリックを学ぶ
この頃、五日市に出入りし始めたとされる
明治10(1877)年2月~6月
神田猿楽町で福田理軒に洋算を学ぶ
明治10(1877)年8月~明治12(1879)年11月
横浜山手で米人マグレーにプロテスタントを学ぶ
9月 小田原で教職に就く
この頃秋川谷各地(大久野、草花)で教職に従事
明治12(1879)年12月~明治13(1880)年4月
東京麹町にて商業に従事
明治13(1880)年
4月 五日市に下宿、勧能学校に勤めはじめる
同じ頃五日市学芸講談会結成
11月 第2回国会期成同盟大会(私擬憲法作成決議)
12月 土屋勘兵衛、嚶鳴社憲法草案入手
明治14(1881)年
春~夏頃 頃五日市憲法草案起草
6月 五日市を去り、奈良橋村へ また、各地(高知、山梨。北多摩)の演説会等に出席
各地へ移動しているこの頃から体調を崩した模様
10月 国会開設の詔勅 勧能学校へ戻り、2代目校長となる
明治15(1882)年
5月頃 結核進行、草津温泉で療養
8月 深澤権八ら自由党に入党
9月 「王道論」脱稿
11月 郷里に一時帰郷
明治16(1883)年
3月 「読書無益論」脱稿
11月12日 本郷竜岡病院にて死去、31歳
『自由民権に輝いた青春 卓三郎・自由を求めてのたたかい』江井秀雄、2002『「五日市憲法草案の碑」建碑誌』五日市町役場、1980の(千葉卓三郎年譜)をもとに作成。